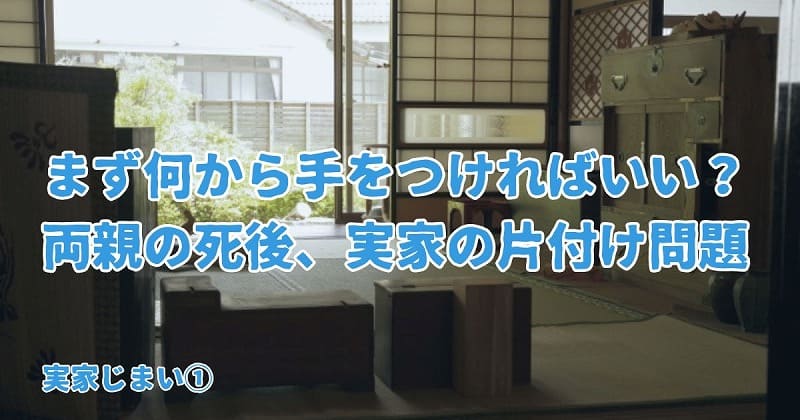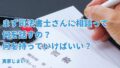親が亡くなった直後
親が亡くなったあと、葬儀や役所の手続きに追われて落ち着いたころに、ようやく「実家じまいをしなければ」と向き合う方も多いでしょう。
けれど、いざ始めようとすると「何から手をつければいいの?」と頭が真っ白になってしまいますよね。特に親子関係が希薄だった人にとってはなんにも分からない状態からのスタートになることだと思います。
私自身も他人事ではありません。近い将来のために「実家じまいの最初の一歩」を整理してみることにしました。
【最初の一歩】実家にある「大事そうな書類」をひとまとめにする
実家じまいのスタートは、まず「書類集め」。
| 書類 | 使い道 |
|---|---|
| 📂遺言書 | 勝手に開封しないこと!有る無しで遺産分割の進め方が大きく変わる |
| 📂権利証・登記簿のコピー | 家や土地を売るときに必要 |
| 📂固定資産税の納税通知書 | 不動産の評価や税金計算に必要 |
| 📂通帳・キャッシュカード・印鑑 | 預金や公共料金の解約などの手続き |
| 📂保険証書や年金関係の書類 | 保険金の請求や年金手続き |
| 📂公共料金の請求書・領収書 | 電気・ガス・水道・電話の解約や精算 |
| 📂証券会社の郵便物 | 残高証明請求や換金(名義変更して運用継続も可) |
| 📂クレジットカード会社、消費者金融、銀行ローンなどの郵便物 | 財産調査の際に必要 |
| 📂ローン契約書や返済計画表 | 財産調査の際に必要 |
| 📂その他「大事そうな書類」 | 後で必要になる可能性があるため保管 |
- 大きめの箱やファイルケースを用意して「大事なもの入れ」として集める
- 仕分けは後回しでOK。まず置き場所をひとつにする
- 「これは要らないかな?」と思っても、とりあえず保管しておく
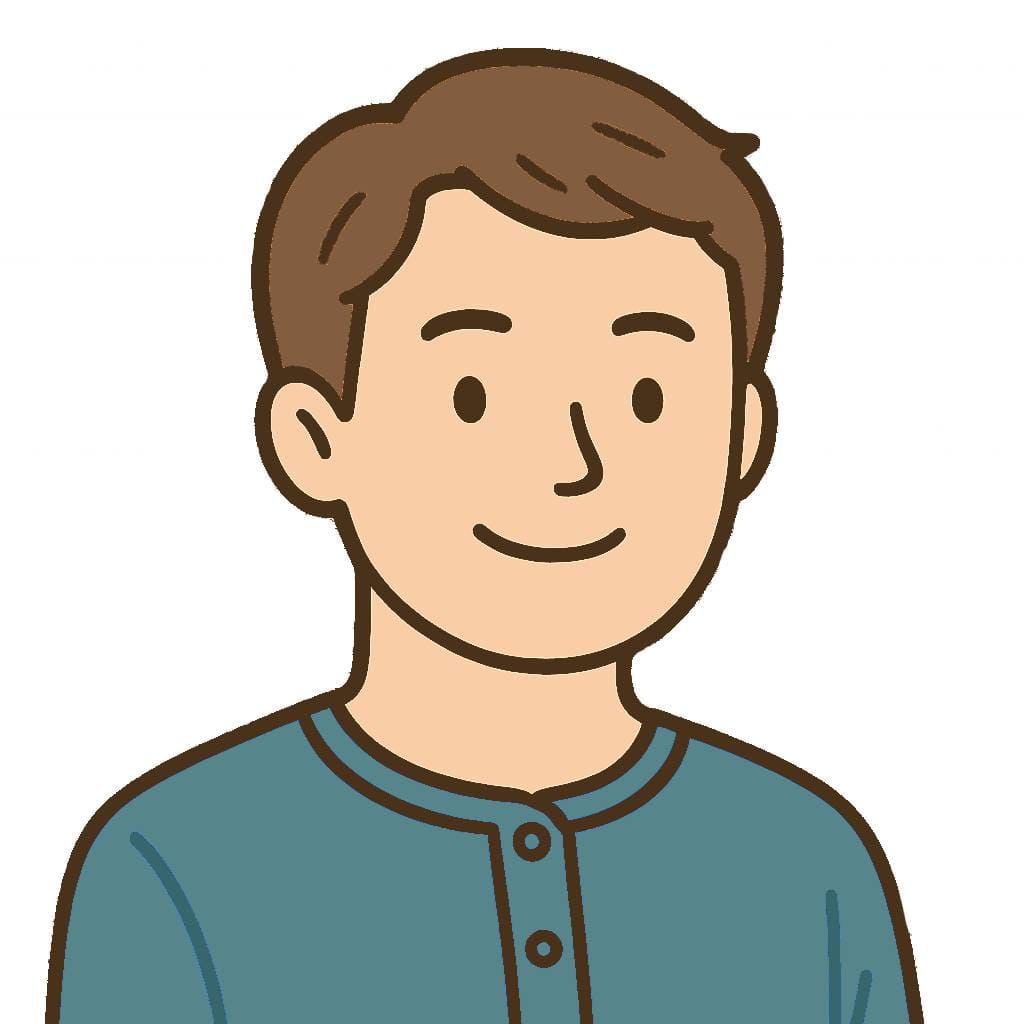
でも、どこに何があるか全然わからないんです…
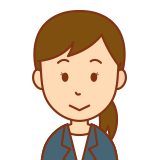
最初は完璧じゃなくて大丈夫。机の引き出しや仏間の棚、よく使っていたカバンなど、思いつく場所からでOKです
特に親子関係が希薄で生前の状況が不明な場合は、借金(マイナスの財産)の徹底調査が先決となります。
- クレジットカード、契約書、ATMでの取引明細、催告書や督促状。通帳に貸金業者からの入金記録や返済の記録がないかも確認が必要。
- 消費者金融やカード会社からの郵便物
- 信用情報機関への開示請求:自宅での調査に限界がある場合は信用情報機関(JICC,CIC,KSCなど)に開示請求を行うこともできます。
- 連帯保証人債務の確認
【次の一歩】市役所の無料相談や司法書士に予約を入れる
必要書類がある程度まとまったら、市区町村役所の無料相談と、専門家に相談予約してみましょう。役所の無料相談「おくやみ窓口」では「役所における手続き」についてサポートしてくれます。
専門家は、司法書士が「相続登記(不動産の名義変更)」に関わることが多いため、最初の専門家相談先によく選ばれます。(財産も負債も不動産もない場合には専門家への相談は不要のケースが多いです)
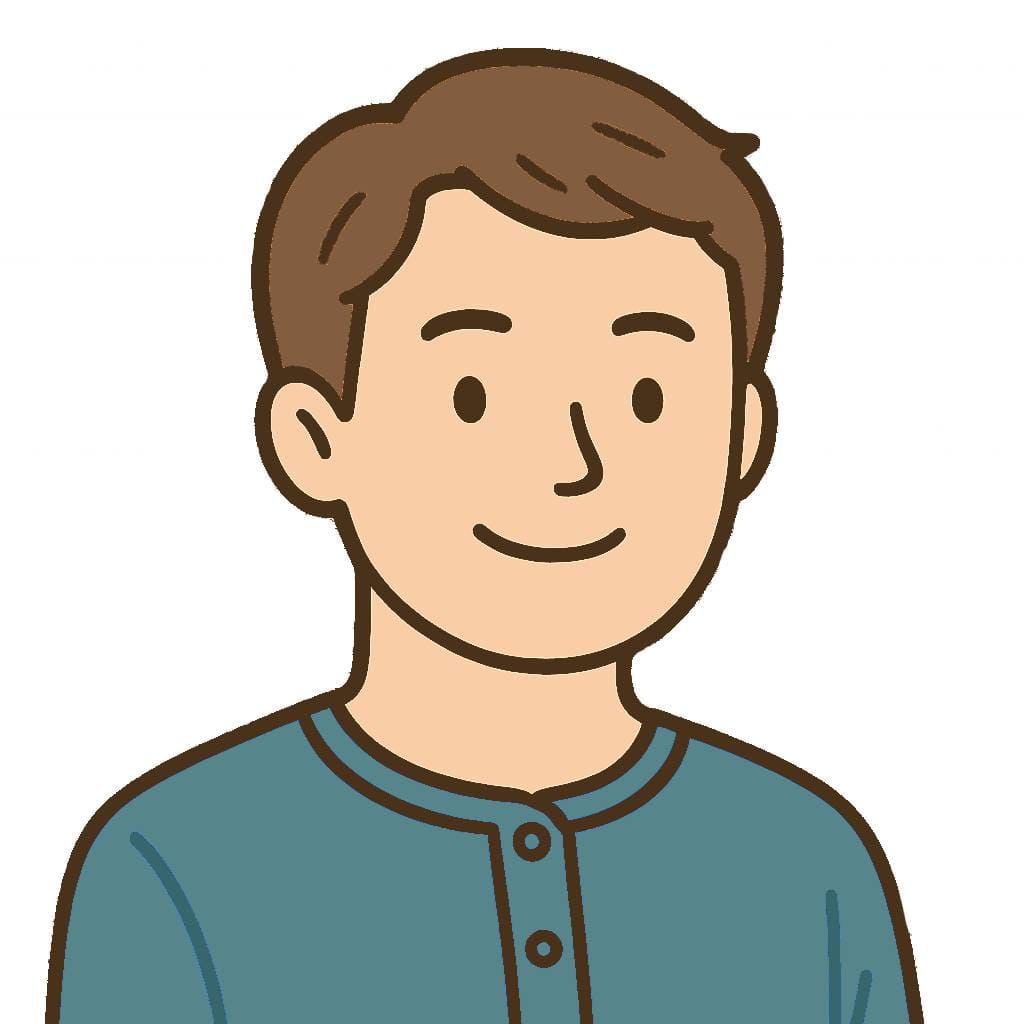
司法書士?行政書士?どっちが何だっけ??
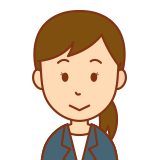
ざっくり言うと、不動産の名義変更は司法書士、遺産分けの書類作成は行政書士です
司法書士と行政書士の違い
🏛️ 司法書士
- 相続登記(不動産の名義変更)が専門
- 法務局への手続き全般を代行
- 遺産分割協議書作成のサポートも可能
📄 行政書士
- 役所への申請書・届出を作成
- 遺産分割協議書や遺言書のサポートが得意
- 不動産の名義変更 → 司法書士
- 相続人同士の話し合いを文書化 → 行政書士
- 実家じまいを進めるなら「まず役所の無料相談コーナー」
- 役所の無料相談コーナーで適切な専門家を紹介してもらえる場合もあります
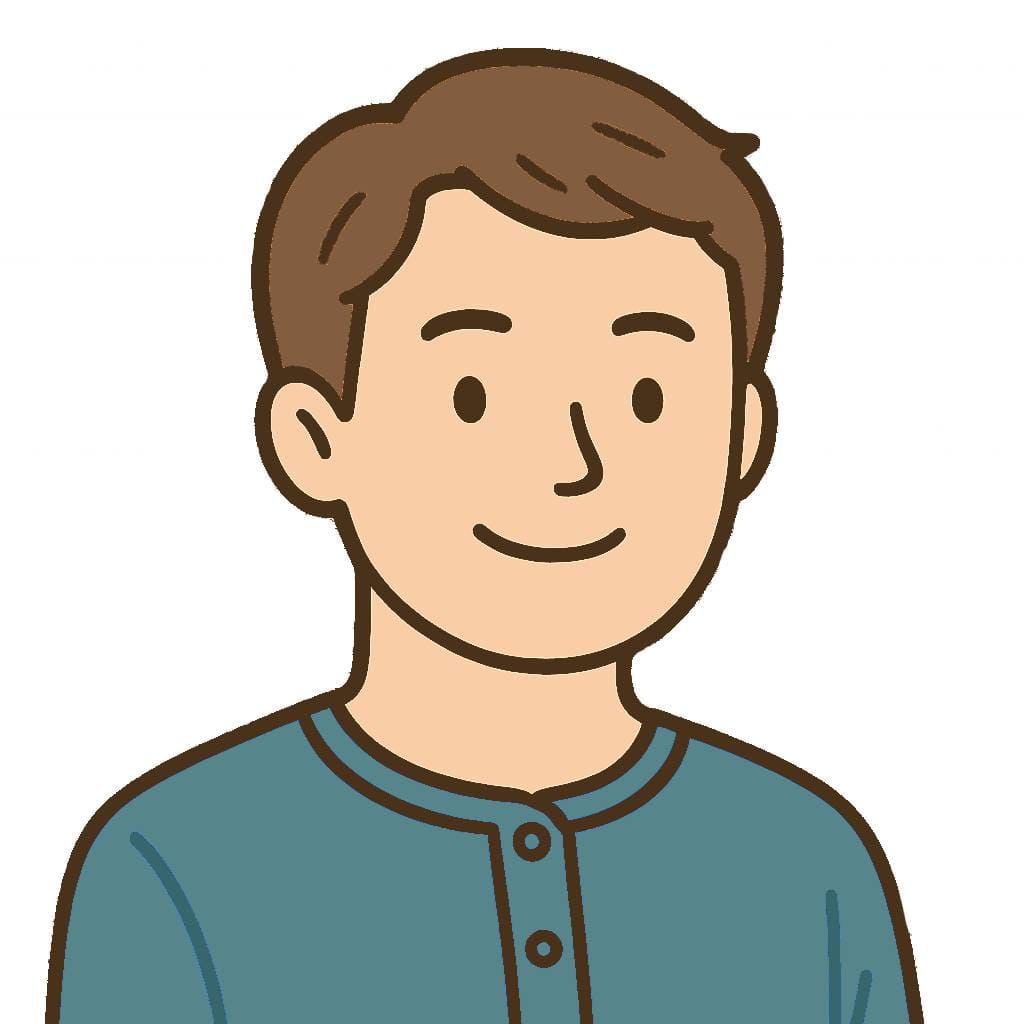
行政書士さんって必ず必要になるの?
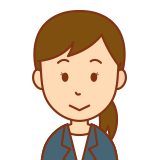
相続人全員が合意して協議書を自分たちで作れるなら不要です。ただ、揉めそうだったり書き方に不安があるならお願いすると安心です

遺言書を確認するタイミング
- 親が亡くなった直後に探す
- 金庫、タンス、引き出し、仏壇など
- 通帳や印鑑と一緒に保管されていることも多い
- 親が信頼できる知人や専門家に預けている場合もある
- 公正証書遺言は、公証役場で保管されている
- 遺言書が見つかった場合
- 勝手に開封してはダメ(自筆での遺言書の場合、未開封のまま家庭裁判所で「検認」の手続きが必要)
👉 遺言があるかないかで、遺産分割の進め方が大きく変わるから、まずは確認が最優先。
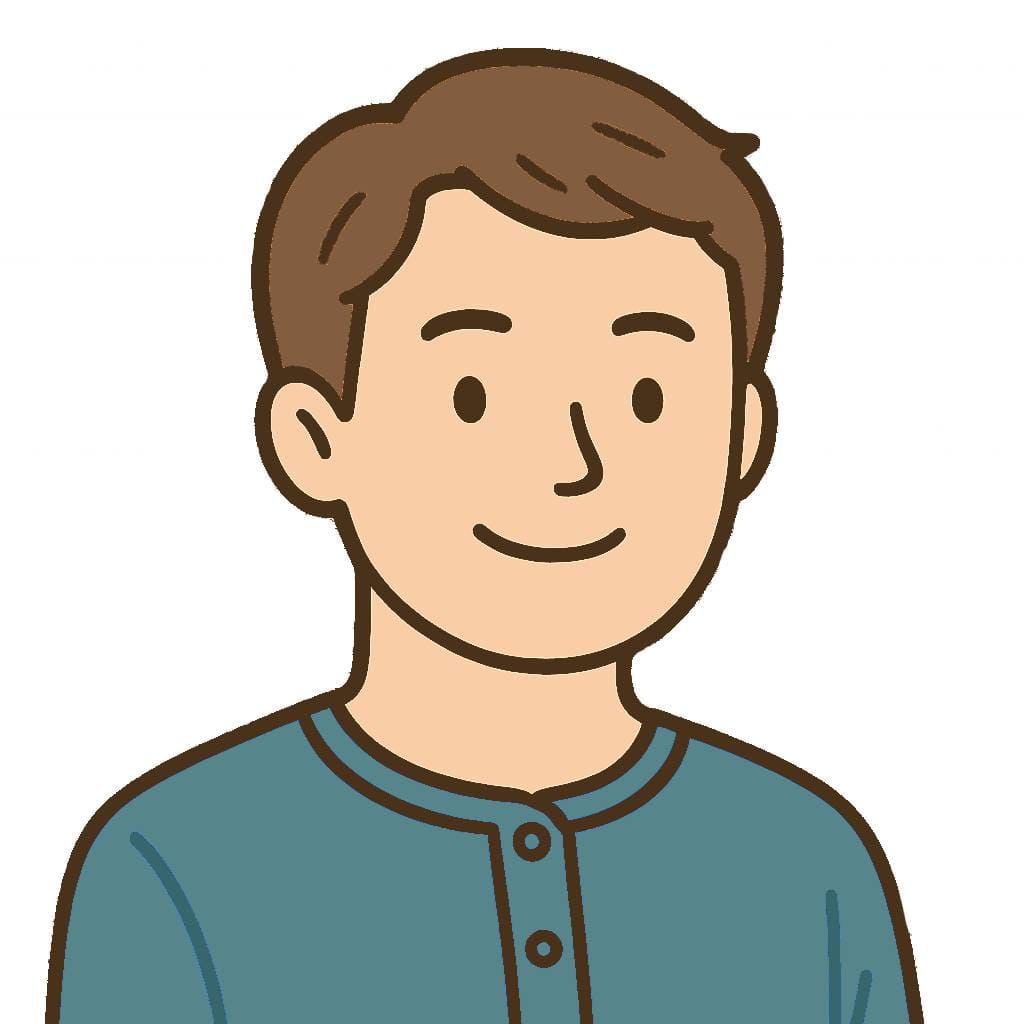
遺言書って法務局や公証役場で保管されている場合、どうやってその存在に気づくの?
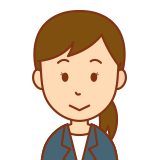
どうやって気づくかは色々シチュエーションがありますが、親が遺言を作ったかどうかもわからないときは、自分で確認する必要があります。
まず、遺言書の種類と保管方法は、このようなものがあります。
- 「自筆証書遺言」を自宅で保管。または貸金庫・信頼できる知人や専門家などに預けるか法務局に預ける。
- 自筆の「秘密証書遺言」を自宅に保管か、貸金庫・信頼できる知人や専門家などに預けることが多い。(証明に2人以上の証人が立ち会う)
- 「公正証書遺言」を公証役場で作って原本は公証役場に預けて保管(作成に2人以上の証人が立ち会う。遺言者には通常『正本』が交付される)
通常は、遺言を作った本人が相続人に「公証役場で作ったよ」「法務局に預けているよ」などと生前に伝えているか、証人になった人から情報をもらえるか、親の遺品から「正本」または「謄本」が出てくるかといった方法でわかるようです。
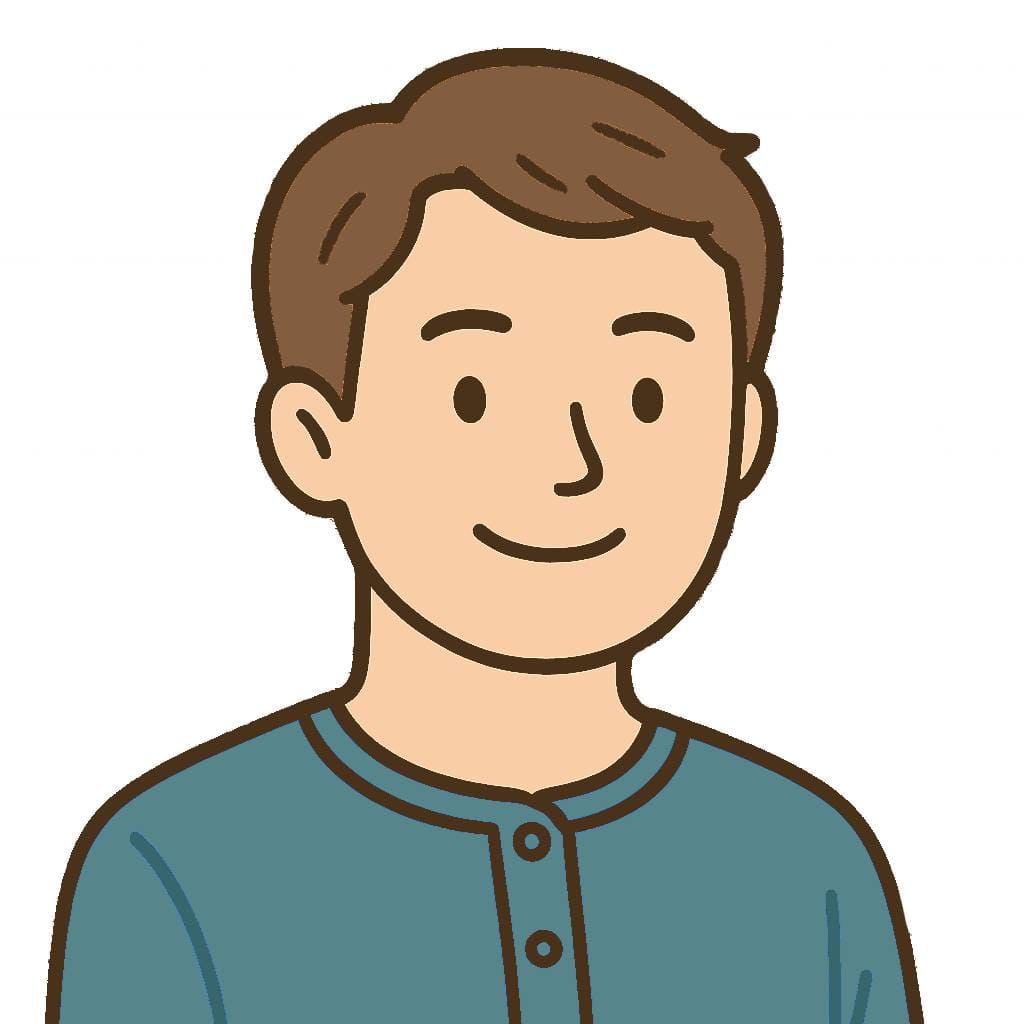
遺言書の違いがよくわからないな
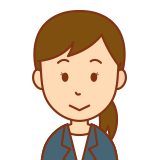
作成時の費用は公正証書が一番高額で有料、秘密証書遺言は有料、自筆証書遺言は無料です。
公正証書は公証人が作成し保管するので有効性が高く改ざんの心配もありません。
秘密証書遺言は遺言者が亡くなるまでその内容を秘密にできることが特徴ですが、内容を公証人が確認しないため、要件不備で無効になることも多いようです。
自筆証書遺言は無料で手軽ですが要件不備・改ざん・破棄のリスクがあります。

遺言の有無を調べる方法
遺言があるかどうか全く分からない場合には、以下の2つをやっておくと安心できそうです。
- 法務局に問い合わせる
相続人が請求すれば、その法務局に遺言書が保管されているかどうかを調べてもらえます。 - 公証役場で遺言の検索をしてみる
全国どこの公証役場でも 「遺言検索システム」で調べてもらえます。
👉どちらの場合も「相続人であることを証明する書類」が必要になります。
👉注意点として、法務局や公証役場で確認できるのは「そこに遺言が保管されているかどうか」だけ。遺言が無ければ『この場所にはありません』とは教えてもらえますが、『全国どこにも遺言が存在しません』とまでは分からない点に注意してください!
その他、死後14日内でやること
- 役所で世帯主変更(死亡から14日以内)
- 役所で国民健康保険証資格喪失届(死亡から14日以内)
- 役所で介護保険資格喪失届(死亡から14日以内)
- 葬祭費、高額医療費の支給申請
役所関連は、まとめて行うと余裕ができそうです。
まとめ
- ✅ 書類をまず集める
- ✅ 司法書士に相談する
この2つで「実家じまい」のスタートラインに立てます。
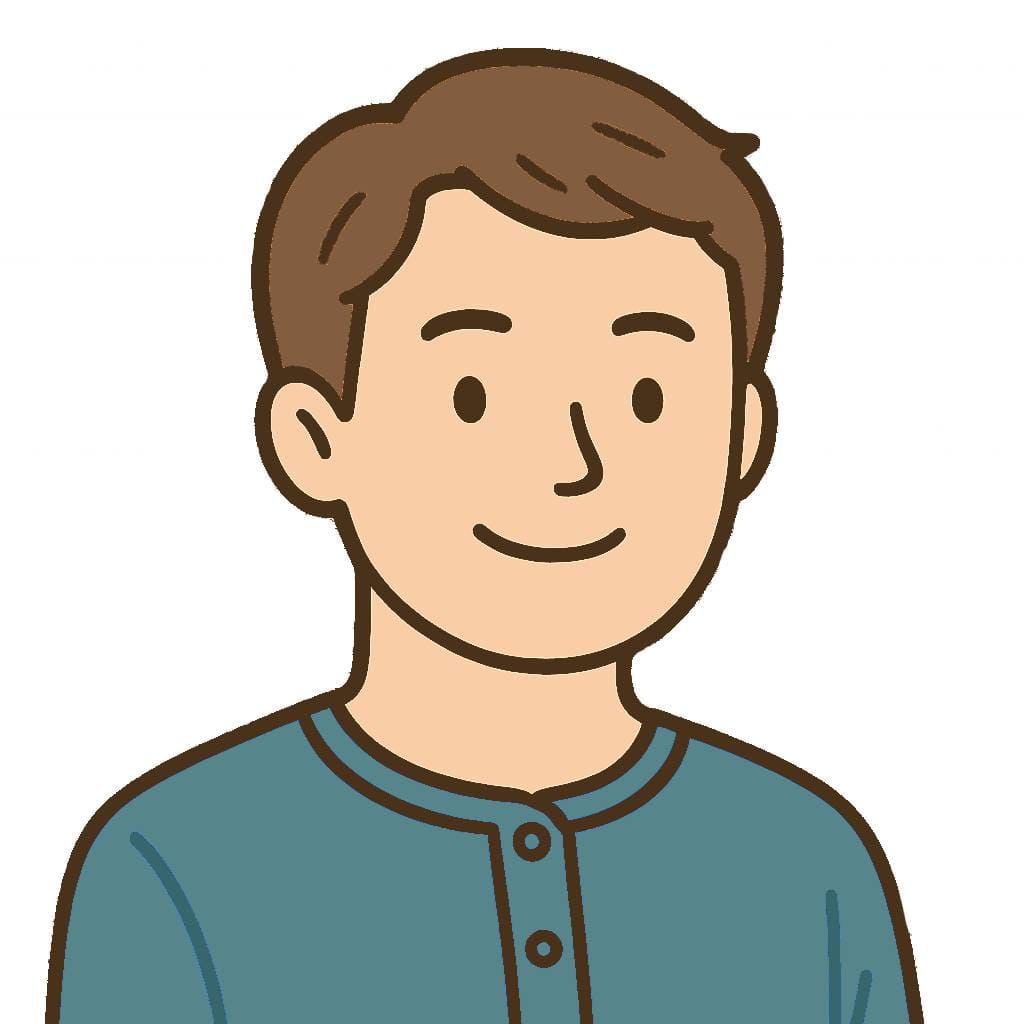
最初の一歩は“書類をまとめる”。それができれば次の道筋が見えてくる!
👉「家族関係や遺産分けが複雑な人」などケースによっては、家の中の物や財産・契約などの確認と、兄弟との話し合いを早期にしておくほうが、司法書士に相談するときに方針が固まっていてスムーズな場合もあります。