故人が生前、ブログやSNS、ネット通販のセラーをしていたなどで収入を得ていた場合はどうすればいいのでしょうか?
今の時代、故人が残す遺産・遺品は「現金や不動産」だけではありません。ブログやSNSアカウント、YouTube、ネット通販など、ネット上の活動や収益も相続財産に含まれる可能性があります。
また、放置しておくと勝手に継続課金されてしまうサブスク契約やサーバー・ドメイン契約を遺される場合もあります。
これらは現実の遺産と違って「どこに何があるのか」「どうやってアクセスするのか」がわかりにくく、家族を悩ませることが多いです。
デジタル資産も相続財産に含まれる可能性があるが、評価や課税方法は専門家への相談が必要!
デジタル遺産・遺品の代表例
- ブログ(+アフィリエイト収入)
- SNS(Instagram、Xなど)(+広告収入)
- YouTubeチャンネル(+広告収入)
- ネット通販でのセラー活動(Amazon、Shopeeなど)
- 個人のホームページ
- サブスク
デジタル遺産 手がかりはどこにある?
故人がネットでどんな活動をしていたか、どんなサービスを利用していたのか分からない時、メールの送受信記録やパソコンのブックマークや検索履歴が手掛かりになります。
- メールの送受信記録
「Amazon」「Seller Central」「Payoneer」「BASE」「Shopify」などのキーワードで検索 - 銀行口座の入出金明細
- ブックマークやショートカットアイコン
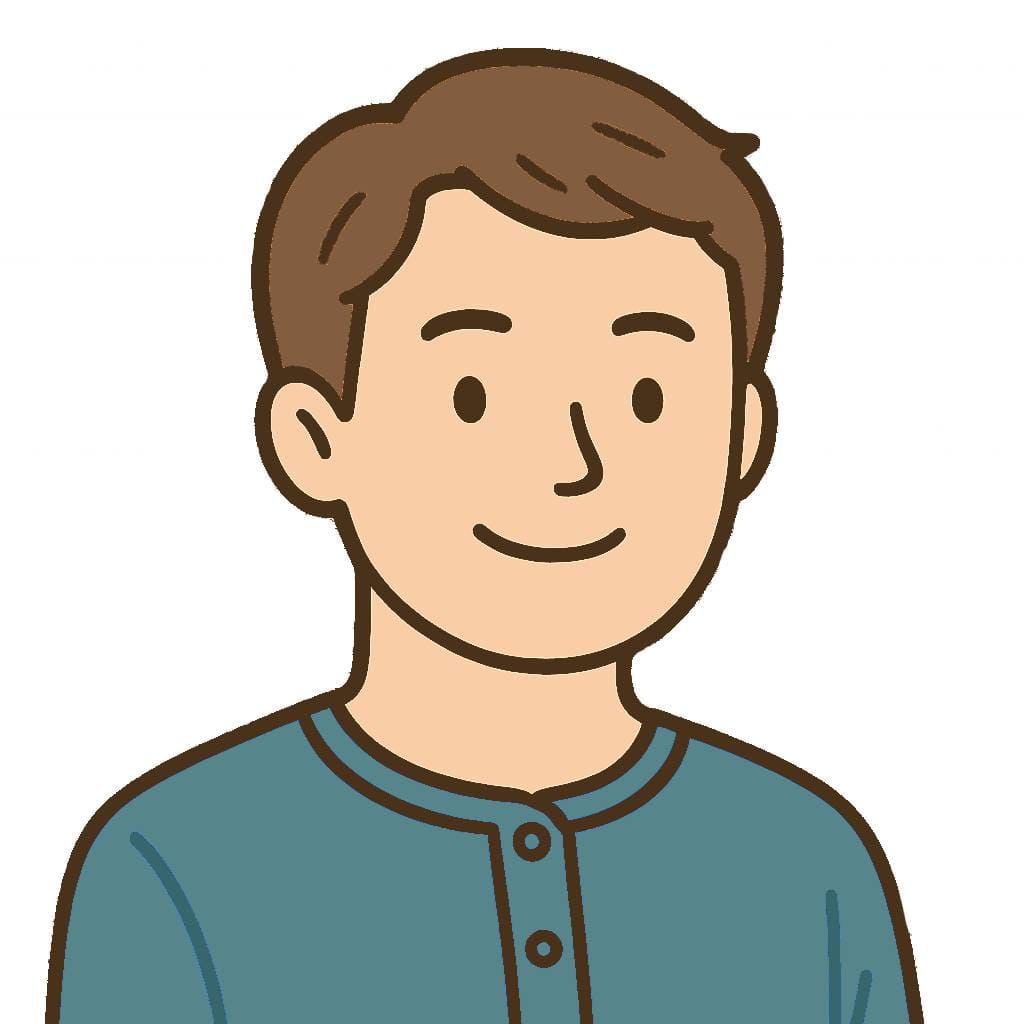
でも、まずパソコンやスマホが開けないと調べようがないよね。パスワードが分からない時はどうしたら?
パソコンやスマホのパスワードが分からないときは?
- パスワードがノートやメモに残されていないか
Googleスプレットシートなどで管理していることもよくあります - パソコンメーカーやスマホキャリアに問い合わせる
問い合わせることはできるが、原則としてパスワードは開示・解除されない - デジタル遺品サポート業者に依頼
パスワード解除・データ抽出などを行ってくれるが限界はある。依頼先はよく選ぶべき
調べてみたところ、デジタル遺品サポート業者というのがあるようです。パスワードの解読やデータの取り出しなどをしてもらえるようですが、限界はあり対応範囲や法的リスクを確認することが大切です。

ノートのメモ書きや、メールの送受信記録・履歴で調べられそうなこと
パソコンやスマホが開ければ、メールやSNSはパスワードが保存されていてそのまま開いて閲覧することができる場合が多いでしょう。
アカウント・ログイン関連
- ☐ SNSアカウント(Facebook、Instagram、X、LINEなど)
- ☐ ブログサービス(WordPress、はてな、Amebaなど)
- ☐ YouTubeや動画配信アカウント
収益に関わるもの
- ☐ アフィリエイトID(ASP*各社のログイン情報)
- ☐ YouTube・SNSの広告収益
- ☐ ネット通販セラー(Amazon、Shopee、eBay など)
- ☐ ネット銀行・PayPay・楽天銀行などの口座
- □仮想通貨・NFT
契約関係
- ☐ サーバー契約(Xserver、さくらインターネットなど)
- ☐ ドメイン契約(お名前.com、ムームードメインなど)
- ☐ ホームページやショップの有料プラン(jimdo、Wix、ペライチなど)
- □サブスク契約(Amazonプライム、Netflix、マネーフォワードなど)
海外・決済関連
- ☐ PayPalやPayoneerなどの外貨送金サービス
- ☐ 越境ECサイト(Amazon、Shopeeなど)
*ASPとは:アフィリエイトサービスプロバイダー(Affiliate Service Provider)の略で、広告主とアフィリエイターを仲介する企業のことを指します。アフィリエイトをしている人の多くは複数のASPを利用していることが多く、各サイトにログインして利用します。

デジタル遺品 各種手続き
ブログやホームページを公開していた場合
無料ブログの場合は運営会社へ死亡したことを伝え、削除や保存、引き継ぎなどの手続きを進めます。引き継げるかどうかは各運営会社の規約によります。
WordPress等の有料ブログを使っている場合はサーバー代とドメイン代の費用がかかっているので、解約をしないと継続課金されてしまいます。
また、無料ブログ(はてな、note、FC2等)であっても有料プランにしている場合もあります。その場合もプラットフォームの解約が必要になります
ホームページを閉じる場合は、個人が契約していたサーバーやドメインを解約する必要があります。
どこかにサーバー情報やドメインの情報がノートなどに書かれていないか、メールにサーバーやドメインの会社とやり取りをしていないかどうかなど調べて、解約を行いましょう。
契約者が亡くなった旨を申し出ればその後の手続きを教えてくれると思います。
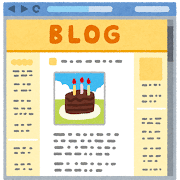
ブログやSNSでアフィリエイト収入、YouTubeで広告収入を得ていた場合
ブログはIDとパスワードがわかればそのまま引き継ぐことが可能な場合もあるようですが、契約内容や利用規約で利用者が死亡した場合をどのように定められているかを確認する必要があります。規約で相続が認められていない場合はアカウントの削除を申請することになります。
アフィリエイトや広告で確定報酬がある場合、振り込まれる口座を相続人のものに変更する必要があります。(相続財産に含まれます)
口座変更は各ASPサイトにログインして設定します。アフィリエイトをしている人の多くは複数のASPを利用していることが多いのでそれぞれで行う必要があります。
ブログでアフィリエイトを行っている人の多くはWordPress等の有料ブログを使っている場合が多いです。こちらはサーバー代とドメイン代の費用がかかっているので、解約をしないと継続課金されてしまいます。
また、無料ブログ(はてな、note、FC2等)であっても有料プランにしている場合もあります。その場合もプラットフォームの解約が必要になります。
| サービス | 引き継ぐことができるか | 遺族の対応 |
| できない | 追悼アカウントに移行か、アカウントの削除 | |
| できない | 追悼アカウントに移行か、アカウントの削除 | |
| X | できない | アカウントの削除 |
| LINE | できない | アカウントの削除 |
銀行口座はネットバンクであっても通常の銀行と同様に「名義人死亡」を届け出て、相続手続きに進むことになります。
ネット上で通販セラー業を行っていた場合
Amazonなどでセラーを行っていた場合は、アカウント情報が見つかればその運営元に「死亡の報告と相続対応」連絡をしましょう。
Amazonセラーセントラルの場合:
「セラーセントラル ヘルプ → テクニカルサポート」から問い合わせ可能。
死亡証明書や戸籍謄本などを求められることがあります。
BASE / Shopify / STORESなどのECプラットフォームでも、
運営会社へ「運営者死亡に伴うアカウントの処理を相談したい」と伝えましょう。
これらのサイトは「利用規約」で「アカウントの譲渡禁止」とされている場合があるため、
運営会社に正式に連絡し、遺族が売上金を受け取れるか・閉鎖できるかを確認するのが正しい手順です。
何か通販を行っていたのは知っているけど何を利用して行っていたのかまではわからない・・・という時もまずはメールを探りましょう。頻繁に連絡が来ているメールがあるはずです。
外貨受け取り・決済サービスにも注意
越境通販をしていた場合はPayoneerのような外貨の受け取りや管理をするサイトや、送金にPayPalを利用していたりすることもあるのでそのあたりも調査して中にお金が残っていないかどうか確認しましょう。
PayPalやPayoneerなどは利用規約上、口座譲渡・相続不可のようで、原則として凍結・残高清算のみ対応してもらえるようです。
有在庫のセラーをしていた場合
在庫品も相続財産になります。
| 種類 | 例 | 相続財産になるか |
| 売上金 | Amazonの入金待ち残高 | なる |
| 在庫 | 倉庫(FBAなど)にある商品 | なる |
| ECサイトのURL/ドメイン | 独自ドメイン | なる場合アリ |
| SNS・広告アカウント | 集客用Instagram・LINE公式など | 基本的に非財産だが営業資産として扱われることも |
状況が複雑な場合は、次のような専門家に頼るとよいです。
- 司法書士・弁護士:相続財産としての扱い方、アカウント閉鎖手続き
- 税理士:ネット収益を含めた相続税の申告
- デジタル遺品整理サービス(例:デジタル遺品整理協会)
デジタル遺産|サブスクや定期購入の確認と解約手続き
銀行口座の入出金記録に謎の支出が定期的に発生していませんか?
もしかするとネット上のサービスのサブスクリプション(定期課金)や物品の定期購入の可能性があります。
入出金記録に記載されている宛先名をインターネットで検索すると、サービス名や提供元を特定できる場合があります。また、メールボックスを「発送しました」「ご利用明細」「自動更新」などのキーワードで検索すると、関連する契約が見つかることもあります。
これらも運営元に契約者が死亡したことを連絡し、解約を申し出る必要があります。
ただし、利用規約によっては契約者本人しか手続きできないケースもあるため、死亡を証明できる書類(戸籍・除籍謄本など)が必要になる場合もあります。
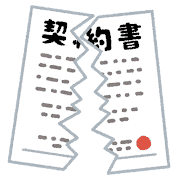
Googleのアカウントがわからなくてメールやスプレットシート等が見れない場合
Googleのサポートページから「故人のアカウントに関するリクエストを送信」し、家族であることや故人の死亡を証明する書類を提出して、アカウントの閉鎖やデータ取得の申請を行う必要があります。
審査の結果、アカウントの閉鎖や、状況によってはデータの一部(Gmail、写真など)の取得が許可される場合があります。
まとめ|デジタル遺産対策
親が急逝した場合、現金や不動産と違って「デジタル遺産」は手掛かりを得にくく、引継ぎがされず放置…という実態が増加しているようです。
メールやスマホのパスワードがわからず、どんなサービスを使っていたのかも調べられないまま、アフィリエイト収入やネット通販の売上が宙に浮いたり契約だけが更新されて費用が発生してしまうこともあるようです。
エンディングノートに「どのサービスを利用しているか」「ログイン方法」「収益が発生しているものの有無」などを簡単に書き残しておくだけでも、残された家族の負担は大きく軽減されます。
私自身もこの記事を書きながら自分はしっかりエンディングノートを準備しておこうと強く思いました。
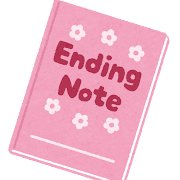
ネットで収益活動をしている人は遺族に負担をかけないよう、生きている間に終活をすることが大事だと思います。
収益が多く出ているブログやECサイトは売買することができます。
「ラッコM&A」は掲載・成約数No.1、成約数シェア約75%(*1*2)売却手数料無料なのでおススメです。
こういった仲介業者に依頼すると、サイト譲渡などの難しい手続きをサポートしてもらえるので安心です。
*1 2021年1月から現在まで(自社調べ)
*2 2023年1月4日時点から過去1年(自社調べ)




コメント