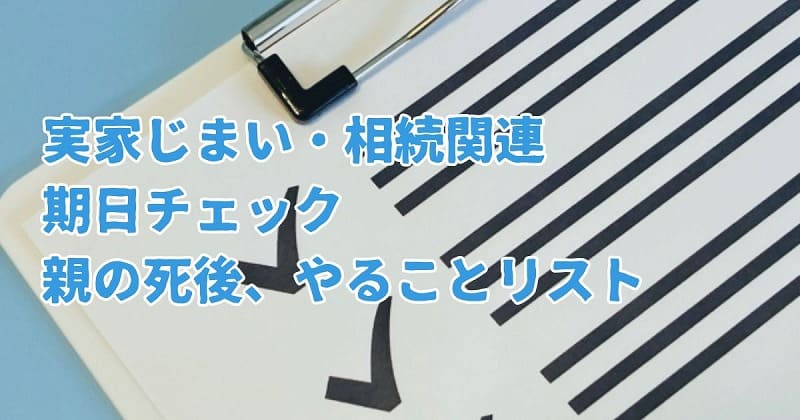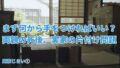親が亡くなると、気持ちに整理がつかない中でも、さまざまな手続きを期限内に進めなければいけないですよね。
死亡届や年金、相続登記、遺産放棄の申請などにはそれぞれ決められた期限があって、遅れると不利益を受けたり余計な手間が増えてしまうこともあります。
「何から手をつければいいのか分からない」「後回しにしたら間に合わないのでは…」と不安になる方も多いでしょう。
ここでは、親の死後に必要となる実家じまい・相続関連の手続きを、期限(タイムリミット)に注目して整理しました。(法要事は省略しています)
※亡くなった人の状況によってはこれら以外にも手続きが発生します。詳しくは役所の無料相談「おくやみ窓口」や専門家にご相談ください。
親が亡くなって直後~7日の初動
最初に心構えをしておくことは、医師から「死亡診断書」をもらったら、すぐさまコピーを5部ほど取ること。これを忘れないようにしましょう。(死亡届と死亡診断書はセットになっています)
火葬の手続きや死亡届の提出などのあたりは葬儀社や病院からあれしろこれしろと結構指示してもらえますので、まだ頭がしゃっきりしていないこのころでもなんとか乗り切れます。
使う葬儀社を決めていなくても、病院から葬儀社リストのファイルを手渡されますのでなんとかなります。
銀行への連絡は急ぎすぎない
銀行は、名義人の死亡が分かるとすぐさま口座を凍結します。すると、すべての支払いや入金がストップしますので、公共料金やクレジットカード、借入金など引き落とし類ができなくなり、あとから振り込まなければならないという手間が増えます。
また、亡くなる前後に預金引き出しをしてしまうと、色々と問題が起きる場合があります。(遺産放棄ができなくなるなど)負債が大きそうだったり財産が複雑だったりする場合には特に注意しておきましょう。
戸籍謄本の取り寄せ
戸籍謄本に親の死亡が反映されるのは10日程度かかるようです。早すぎると反映されていないので10日たってから取り寄せます。
法定相続情報証明制度を利用
法定相続情報証明制度とは、2017年から始まった新しい制度で、相続手続きをするときに 戸籍一式を何度も提出しなくてよくなる、とても便利な仕組みです。
従来の方法
銀行や法務局、不動産登記、年金、保険の手続きなどで、「誰が相続人か」を証明するために、
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を、各手続き先ごとに何部もコピーして出さなければならなかった
法定相続情報証明制度を使うと
- 相続人が「相続関係図(家系図のようなもの)」を作る。
- 必要な戸籍謄本などをそえて、法務局に提出。
- 法務局が確認してくれると、「法定相続情報一覧図の写し」を発行してくれる。
その一覧図は、公的な証明書として扱われるから、
銀行・保険・登記など、いろんな手続きに同じ書類を使い回せる。
| メリット | 説明 |
| 戸籍を何部も集めなくていい | 1回まとめて法務局に出すだけ |
| 手続きがスムーズ | 不動産登記・銀行手続きなどでスピードアップ |
| 無料で発行できる | 発行手数料は0円(コピーの追加分も無料) |
| 代理人でも申請できる | 司法書士・行政書士・弁護士に依頼も可能 |
申請先は、下のいずれかを管轄する法務局(登記所)
- 被相続人の本籍地
- 最後の住所地
- 相続人の住所地
主な必要書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続関係説明図(相続関係を示した図)
- 申出書(法務局のサイトに書式あり)
故人が飼っていたペットの処遇
この時期ではまずは一時預かりや通いで世話をしてくれる人を決めるのが先決でしょう。命のことなので忘れないで行いたいものです。
期日チェック表
| 項目 | 期限 | 備考 |
|---|---|---|
| 通夜 | 一般的に亡くなった翌日 | 火葬場や寺院、遺族の都合、地域の慣習などによって日程が調整されることも |
| 死亡届の提出 | 7日以内を目安 | 葬儀社が代行してくれることが多い。死亡届と死亡診断書は5枚ほどコピーを取っておくこと |
| 死体火葬埋葬許可申請 | 火葬前に。死亡届の提出と同時に | 葬儀後の火葬には、役所からの許可が必要 |
| ペットの処遇 | 早めに | もし実家でペットを飼っていた場合、一時預かりや世話をする人 |
| 葬儀 | 5日以内 | 亡くなった翌々日~5日以内が一般的 |
| 遺言書の確認 | 親が亡くなったらすぐ探す | 【弁護士・司法書士相談可】自筆遺言書は家裁で検認要。相続登記や遺産分割の進め方が変わるので早く |
| 戸籍謄本の取り寄せ | 死亡から10日経って死亡が戸籍に反映されたら | ・被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍 ・相続人全員の現在の戸籍謄本 |
| 法定相続情報証明制度の申請 | 戸籍謄本を取り寄せたら | 被相続人の本籍地、最後の住所地、相続人の住所地のいずれかを管轄する法務局で申請できる |
| 世帯主変更 | 死亡の事実が発生してから14日以内 | 役所の住民票や戸籍を扱う窓口 亡くなった人が世帯主だった場合 |
| 介護保険資格喪失届 | 死亡の事実が発生してから 14日以内 | 役所の介護保険担当窓口へ提出 |
| 国民健康保険証資格喪失届 | 死亡の事実が発生してから 14日以内 | 役所の保険・年金関連を扱う窓口へ提出 |
| 市区町村の葬祭費支給申請(国保の場合) | 死亡から 2年以内 | 役所 国保・後期高齢者医療保険加入者が亡くなった場合 申請要 役所ごとはまとめて行うと◎ |
| 年金手続き(未支給年金・遺族年金請求) | 未支給年金は相続遺産となるため3か月以内までに金額確認 | 未支給年金の請求は5年以内が期限。遺族年金には5年の時効があるので注意。窓口:年金事務所、日本年金機構 |
| 借金の徹底調査 | 生前の状況が不明の場合緊急性高 | 自宅を捜索し手掛かりを見つける |
| 銀行預金 | 相続遺産となるため3か月以内までに残高確認 | 相続者が決まれば換金・解約は原則 5年以内 |
| 証券会社 | 相続遺産となるため3か月以内までに残高確認 | 死亡時点評価で相続税対象。相続者が決まれば換金or名義変更 |
| 高額療養費の支給申請 | 相続遺産となるため3か月以内までに金額確認 | 請求期限は診療月の翌月1日から2年以内に 窓口:協会けんぽ・健康保険組合・国保 |
| 介護保険の還付金 金額確認 | 相続遺産となるため3か月以内までに金額確認 | 介護保険資格喪失届を出したのちに市区町村が再計算を行い、過誤納があった場合「介護保険料還付通知書」や「過誤納金還付請求書」などの書類が郵送される |
| 家財や骨董品、貴金属、絵画などの把握 金額確認 | 相続遺産となるため3か月以内までに金額確認 | 相続が決まるまで勝手に捨てたり売ったりしてはいけない |
| 車・バイク | 引き継ぐなら相続財産に含まれるため3か月以内までに金額確認 | 廃車手続きは法定期限なしだが放置すると自動車税や保険料がかかる |
| 遺産分割協議書の作成 | 期限はないが相続手続きの「土台」となる | 【弁護士・司法書士相談可】名義変更・換金手続きの前に作る。遺産放棄や限定承認する場合、どうするか判断した後で作る |
| 遺産放棄の申請 限定承認の申請 | 自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内 | 【弁護士・司法書士相談可】家庭裁判所 に申立て。3か月を過ぎると、自動的に「単純承認(全部相続する)」になる |
| 相続税の申告 | 相続開始から10か月以内 | 【税理士推奨】自分でも可能だが難易度高 |
| 借家・賃貸契約の解約 | 室内の物を撤去できる日を目安に解約 | 貸主への解約通知。契約によっては 1〜2か月前通知が必要 |
| 電気・ガス・水道・電話の解約や精算 | 法律上期限なし (早め推奨) | 契約者が亡くなっても自動停止しない |
| 埋葬料の請求(社会保険) | 2年以内 | 在職中(健康保険協会や健康保険組合加入中)の死亡や、退職後に「任意継続被保険者」になっていた場合等に請求できる |
| 死亡一時金請求(国民年金の場合) | 2年以内 | 条件を要確認(日本年金機構) |
| 家、土地の相続登記(名義変更) | 相続開始から3年以内 | 【司法書士推奨】違反すると10万円以下の過料の可能性。変更後に売却や処分が可能 |
| 火災保険の名義変更 | 相続後すみやかに | 不動産の名義が変更されたらすぐに行います |
| 保険金の請求 | 原則:3年以内 | 受取人が亡くなった人(または受取人未指定)の場合は相続財産に含まれるので注意が必要 |
| スマートフォン解約 | 法律上期限なし (早め推奨) | 大事なデータがあれば移してから、なるべく早めに解約 |
| クレジットカード解約 | 法律上期限なし (早め推奨) | 自動引き落としの設定がある公共料金やサブスクは、カード解約前に設定変更しておく |
| サブスク・定期購入の解約 | 法律上期限なし | 定期的に自動で届くものをストップ |
| 郵便物・通信サービスの整理 | 法定期限なし (早め推奨) | 転送・解約でトラブル防止 |
| 免許証 | 返納の義務なし | 義務は無いが悪用防止のため推奨される。警察署か免許センターへ |
| マイナンバーカード返納 | 法律上期限なし | 市区町村に返納または裁断して破棄 |
| 家屋・土地の管理・固定資産税の支払い | 法定期限なし (年度内の支払い) | 毎年1月1日時点の所有者に課税される |
| 銀行や証券会社 | 換金や名義変更。相続者が決まれば銀行の換金・解約は原則 5年以内 | |
| 車・バイクの保険 | 法定期限なし | 解約や名義変更。 |
| 不動産の売却や処分 | 法定期限なし | 売却や処分の際には火災保険の解約も忘れずに |
※「相続開始日」とは、親が死亡した日です。
※「死亡の事実が発生した日」とは原則として「死亡診断書に記載された死亡した年月日」を言います。ただし、失踪宣告や認定死亡など、ケースによっては法律で死亡とみなされる日が「死亡の事実が発生した日」となることもあります。
※「自己のために相続が開始したことを知った時」とは実際に亡くなった日ではなく「死亡を知った日」。離れて暮らしていて知るのが遅かった場合や被相続人に隠し子がいて、自分が相続人だと知らなかった場合に、実際に知った日からカウントされます。
一次情報リンク
| 項目 | チェック内容 | 参考リンク(公式・一次情報) |
|---|---|---|
| 役所の無料相談 | おくやみ窓口など | 例:中野区おくやみ窓口のご案内 |
| 死亡届 | 死亡届…7日以内を目安 | 総務省(戸籍法86条) |
| 葬儀 | 葬儀…数日内が一般的 | 地域慣習のため自治体HP参照 |
| 健康保険・年金手続き | 年金・保険…14日以内を目安 | 日本年金機構:年金の受給停止 |
| 相続放棄・限定承認 | 放棄・限定承認…3か月以内目安 | 裁判所:相続放棄の申述 |
| 相続人の確認 | 相続人の確認…戸籍をたどって | 法務局:相続手続案内 |
| 埋葬料の請求 | 退職後に「任意継続被保険者」になっていた場合等 2年以内 | 加入していた健康保険協会・健康保険組合で確認してください |
| 高額療養費の請求 | 診療月の翌月1日から2年以内 | 協会けんぽ・健康保険組合・国保等のHPで確認してください |
| 死亡一時金請求(国民年金) | 条件を要確認 2年以内 | 死亡一時金を受けるとき |
| 相続登記(不動産) | 相続登記…3年以内を目安 | 法務局:相続登記義務化 |
| 銀行口座・クレジットカード | 口座・カード…早めに手続き | 契約先の公式ページを確認してください |
| 公共料金・契約関係 | 公共料金…名義変更や解約 | 契約先の公式ページを確認してください |