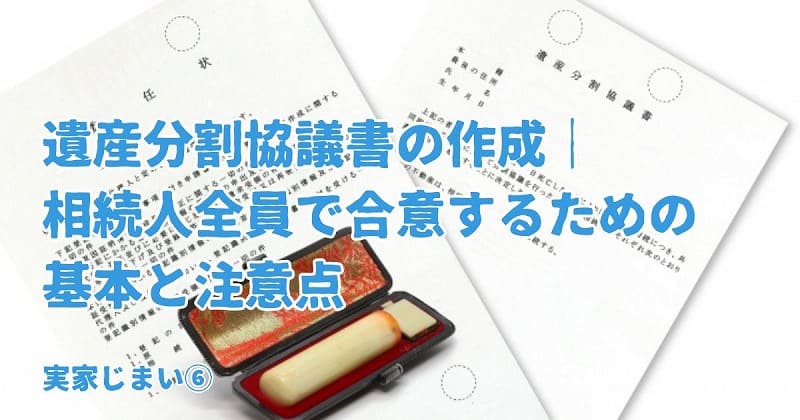遺産分割協議とは?
両親が亡くなったあと、相続人が複数いる場合には「誰がどの財産を相続するのか」を話し合う必要があります。これを 遺産分割協議 と呼びます。
協議の結果をきちんと書面に残したものが「遺産分割協議書」です。
実は遺産分割協議書は法律上の「絶対義務」ではないようです。相続人が複数いる場合、口約束だけで進めると、後から「そんな話は聞いていない」とトラブルに発展することもあるため、書面に残しておくことが大切ということになります。(つまり相続人がひとりしかいない場合は協議も協議書も不要)
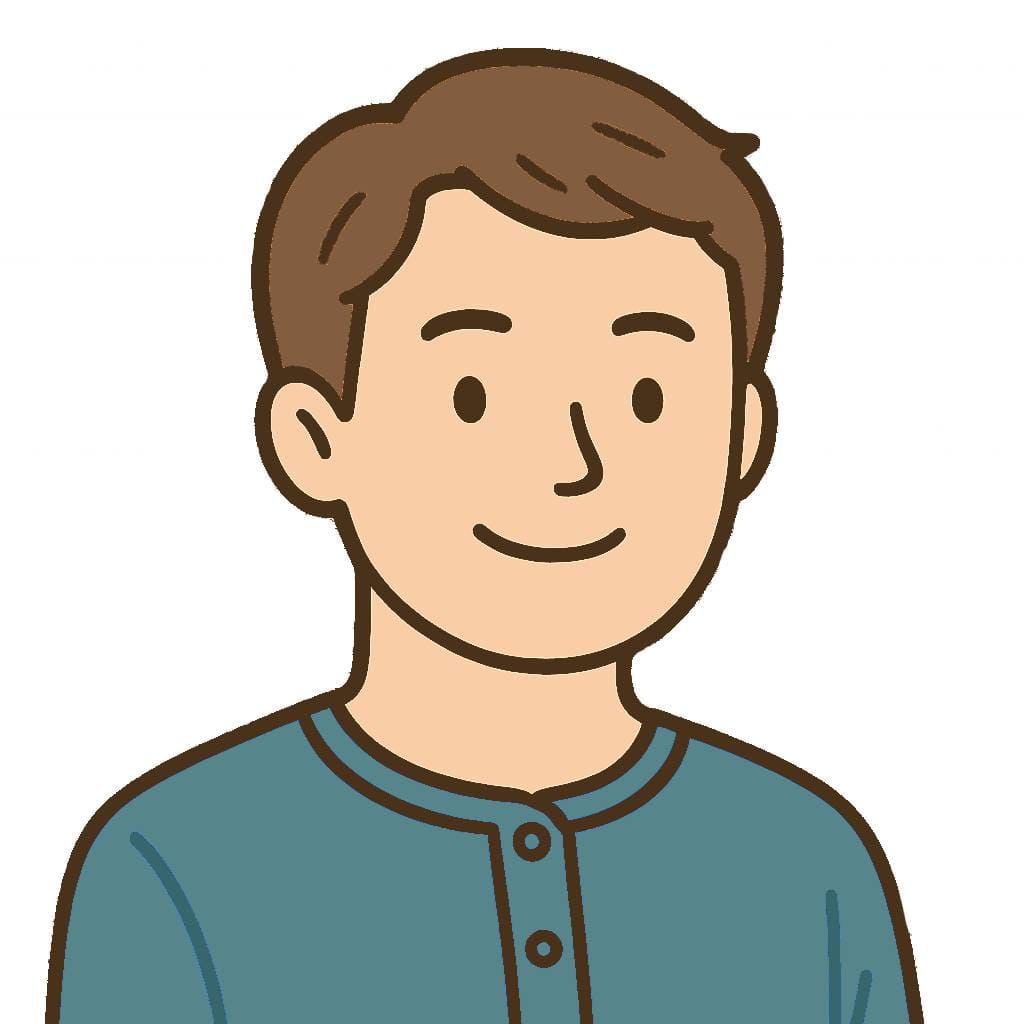
相続人が一人だけのときでも、相続放棄や限定承認を検討する材料にはなるから、目録は作るべきだよね。
遺産分割協議書を作成する手順
1. 相続財産の一覧(目録)を共有する
故人が残した財産の目録を改めて共有します。
- 預貯金口座
- 不動産(土地・建物)
- 株式・投資信託などの金融商品
- 自動車・貴金属・美術品
- 借金や未払いの負債
👉 財産調査、目録については、前回の「④財産調査のチェックリスト」を参照
2. 相続人全員で話し合う
相続人が一人でも欠けていると協議が無効になります。
- 兄弟姉妹や配偶者など、法定相続人全員に声をかける
- 揉めそうな場合は、最初から専門家を交えて進めると良さそうです

3. 相続放棄・限定承認がある場合
相続放棄した人は「最初から相続人でなかった」扱いになるため、遺産分割協議には参加しません。放棄の申述が家庭裁判所で受理されたことを確認してから協議を進めましょう。
限定承認をした場合は、相続財産の範囲内で債務を返済することが前提になります。協議書を作るときも「限定承認の内容を踏まえた分割」にしなければならず、弁護士や税理士への相談が欠かせません。
👉これらの手続きは家庭裁判所への申述や債務整理が絡むため、専門家(弁護士・司法書士)に確認して進めることをおすすめします。
4. 協議の内容を文書にまとめる
協議書には、次のような内容を明記します。
- 相続人全員の氏名と住所
- 誰がどの財産を相続するか(具体的に)
- 協議成立日
- 相続人全員の署名と実印押印
- 各相続人の印鑑証明書を添付
遺産分割協議書のサンプル雛形
「○○銀行△△支店の普通預金口座番号××××××は、長男Aが相続する。」
「□□市□□町の土地・建物は、長女Bが相続する。」
のように、一つひとつの財産について具体的に記載していきます。
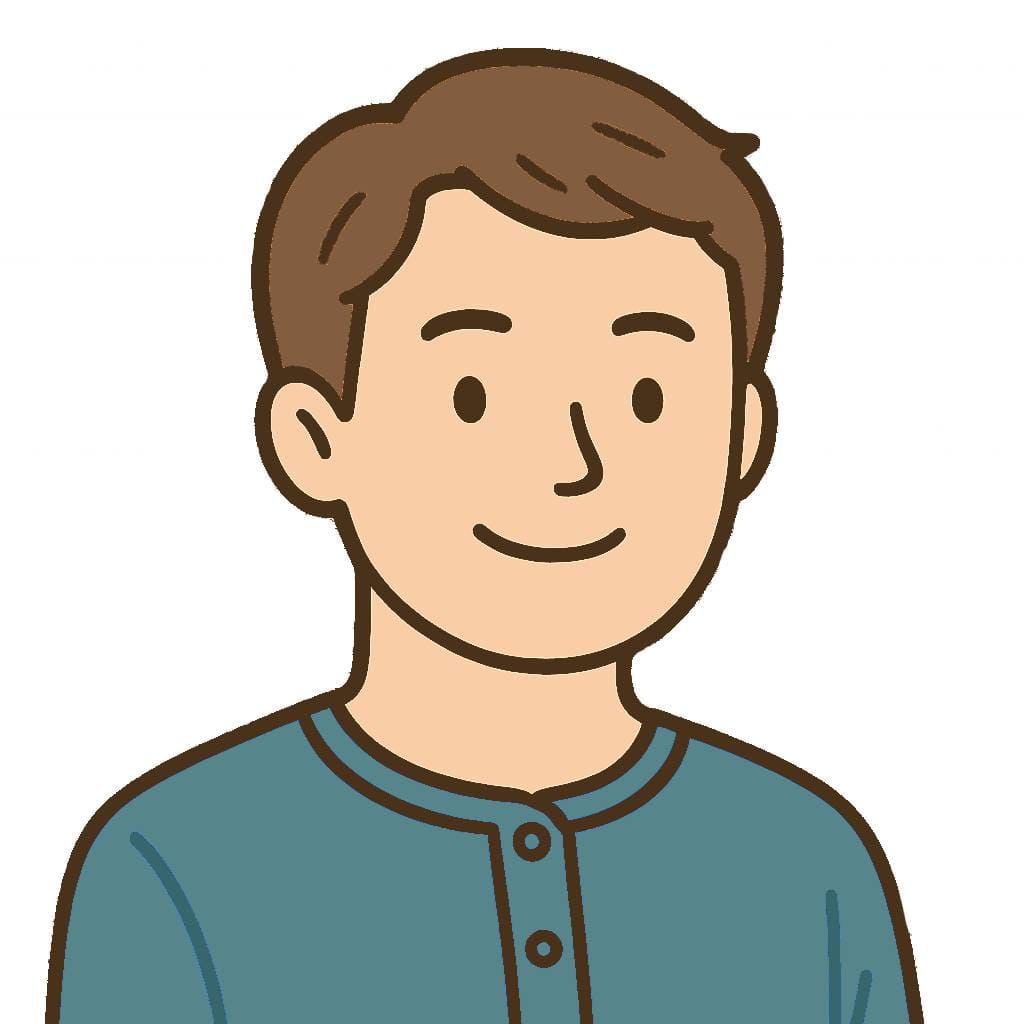
遺産分割協議書には共通の書式はないんだね。
👉ネット上に法務局や司法書士会が公開している雛形があるので、それを使用させてもらうと安心です。
専門家に相談したほうがいいケース
| ケース | 適した専門家 | 補足 |
|---|---|---|
| 相続人同士の意見が対立 | 弁護士 | 交渉・調停・訴訟まで対応可能。揉めているなら弁護士一択。 |
| 相続財産の種類が多く複雑 | 税理士+司法書士 | 税理士=評価・税金、司法書士=登記。連携がスムーズ。 |
| 不動産を複数人で共有したい | 司法書士(登記)+必要に応じて弁護士 | 共有登記は司法書士。将来の揉めごと回避へ合意書は弁護士に相談。 |
| 相続放棄や代償金が絡む | 弁護士(状況により司法書士) | 放棄申述・代償金交渉は弁護士の領域。書式作成は司法書士も可。 |
👉こうした場合は、司法書士や弁護士に相談することで後のトラブルを防ぐことができます。無料相談を利用できるサービスもあります。
失敗しないための注意点
- 必ず書面化する:口頭合意はトラブルのもと
- 全員の署名・実印が必要:1人欠けても無効
- 印鑑証明を添付:後の登記や銀行手続きで必須
- 財産の記載を具体的に:曖昧な表現は避ける
遺産分割協議で相続人が持参するもの
1. 身分確認・印鑑関連
- 実印(シャチハタ不可)
- 印鑑証明書(発行から3か月以内が望ましい。協議書に添付)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
2. 相続関係を確認できる書類
- 戸籍謄本(被相続人との関係を証明するため)
- 住民票または戸籍の附票(相続人の住所を証明)
👉 相続人が多い場合は、まとめて司法書士に依頼すると整理がラクになります。
3. 協議の対象となる財産に関する資料
- 不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書
- 預金通帳や残高証明書
- 株式や投資信託などの証券関係書類
- 自動車の車検証(自動車が遺産に含まれる場合)
4. 遺言書(あれば)
- 公正証書遺言の場合:正本または謄本
- 自筆証書遺言の場合:家庭裁判所での「検認済証明書」が必要
実務でよくあるお金の扱い:まとめ役が立て替えた費用
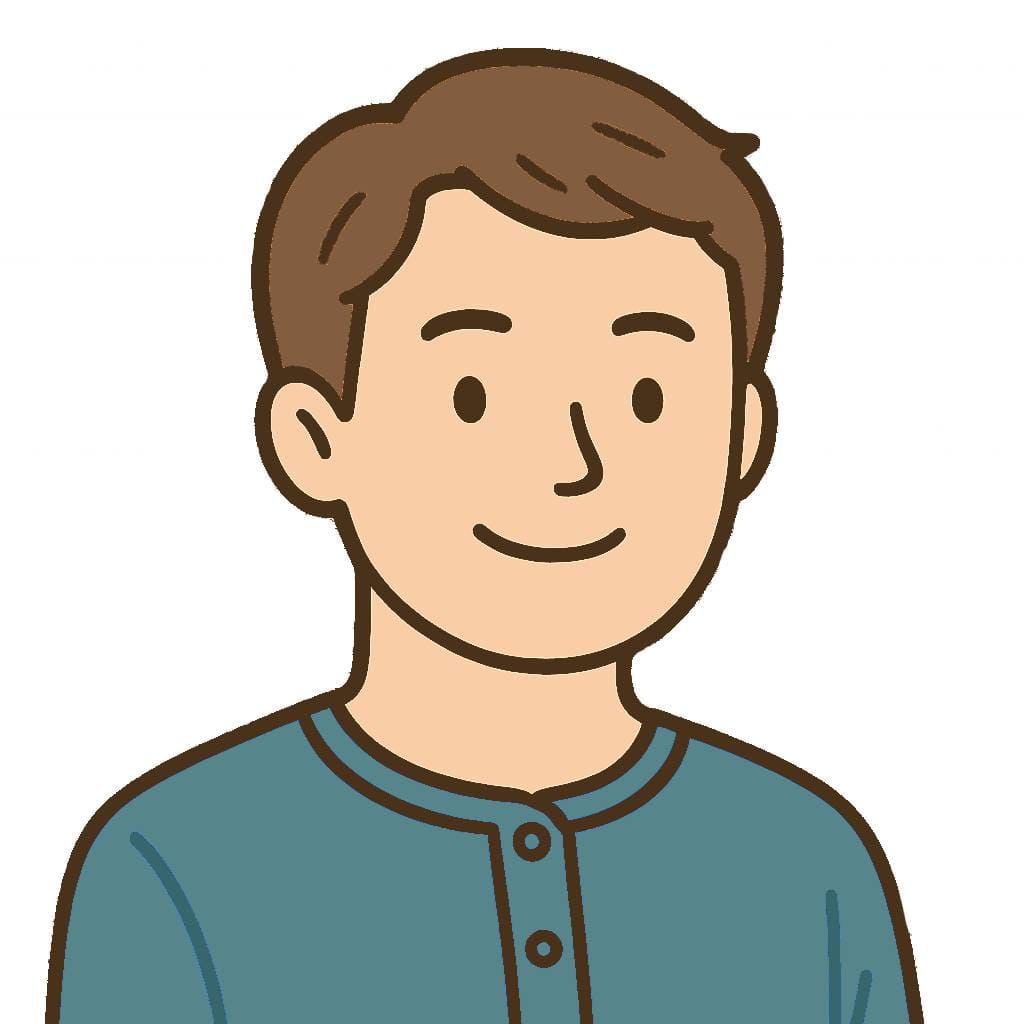
ところで、もろもろ相続の手続きをしていくには、誰かひとりがメインに動いて事務的なことをしたり、細かい支払いを立て替えたりすると思うんだ。そういうお金はどう扱うの?
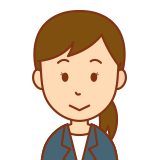
遺産分割協議を進めるときには、どうしても誰かひとりが「まとめ役」として動き、戸籍の取得や司法書士への依頼、細かな事務作業を担うことになります。
その過程で発生する費用を一時的に立て替えることも少なくありません。
立て替え費用の扱い方
- 相続に必要な費用は相続財産から精算
葬儀費用、戸籍謄本代、印鑑証明代、登録免許税などは、原則として相続財産から控除して精算するのが一般的です。 - 領収書を必ず残す
「本当に払ったのか?」という疑念を防ぐために、領収書や振込明細は必ず保管しておきましょう。できれば一覧化して相続人全員に共有すると安心です。 - 遺産分割協議書に明記する
協議書に「相続人Aが立て替えた費用△△円については相続財産から精算する」と記載しておくと、後からのトラブル防止になります。
注意点
立て替えが代表者に偏りがちなので、「こまめに清算する・書面に残す」ことが信頼関係を守るコツです。
まとめ
遺産分割協議書は、相続人全員の合意を「形」にする大切な書類。後々のトラブルを防ぐためにも、財産の洗い出しから相続人全員での話し合い、協議書の作成まで丁寧に進めるのが安心です。
不安な場合は司法書士などの専門家に早めに相談して、スムーズに実家じまいを進められるようにしましょう。